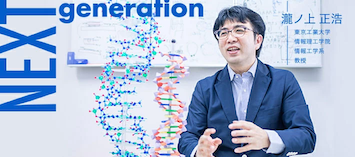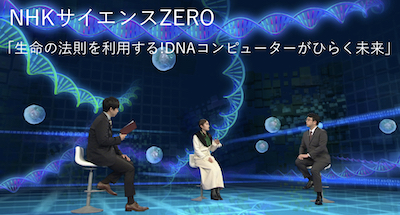template_introduction
情報生命物理学研究室
Intelligent Living Soft Matter Physics and Molecular Computing
|
研究紹介記事等 |
|
当研究室では
生命システムが、物理・化学エネルギーで動くある種の自律的な計算システムだと考え、
・分子反応をプログラミングする計算原理「分子コンピューティング」の情報科学
・非平衡のソフトマターによる知的な「人工細胞」の物理学
の開拓を行っています。
情報・生命・物理の融合で知的な物質を扱う新しい科学を開拓
「生物」と「無生物の物質」は、物質でできている点では同じですが、大きな違いがたくさんあります。たとえば、持っている遺伝情報から自己組織的に体を作ったり、周囲の状況に自発的に適応したり、互いに相互作用しながら集団でより高次の機能を創発したりする点などです。これらの機能は、非平衡系で物質・エネルギーを使ったある種の情報処理(計算)であると考えられます。つまり、生物とは、自律的に‘計算’ができる特殊な物質であると言えます。
物質を扱う科学と情報を扱う科学が高度に発展した今、生物のように情報処理ができる知的な物質を取り扱う物理学、情報科学、生命科学などが必要ですが、これらの古典的な学術の分け方だけではアプローチが困難です。そこで、当研究室では、これらの分野を融合し、知的な物質を取り扱える、分野横断的な新しい科学を開拓することを目指し、下記の研究を進めています。
これらの研究を通して、物理や情報の立場から「生命とは何か?」という根源的な問いを解明するとともに、化学エネルギーを情報処理に変換して動き・考える分子集合体の物理科学を創造し、分子コンピュータや分子ロボットなど、新たなサイエンスを開拓します。